WILL�i�r�i�E�B���i�r�j����s�����w�E�m�E�����E�w�K���T�C�g
���́^�������w���V���E�v���W�f���gFamily�E�����o�ŁE�X�㋳�猤�����E���c���猤�����E���C���C�l�b�g�A��
WILL�i�r�i�E�B���i�r�j����s�����w�E�m�E�����E�w�K���T�C�g
���́^�������w���V���E�v���W�f���gFamily�E�����o�ŁE�X�㋳�猤�����E���c���猤�����E���C���C�l�b�g�A��
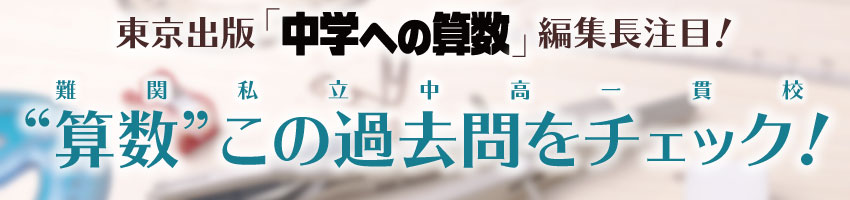

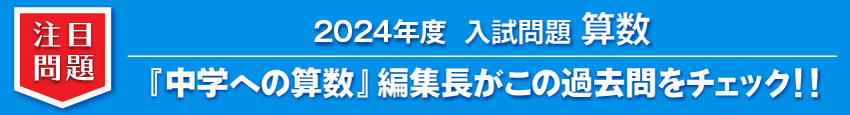
A�N�CB�N�̓�l�ŁC���̐Ύ��Q�[�������܂��B
�Ⴆ�C�͂��߂�20�̐�����܂��B
�@ �`�N��5�̐����܂����B
�A �a�N�͎c����15�̐���U�̐����܂����B
�B �`�N�͎c�����X�̐���P�̐����܂����B
�C �a�N�͎c�����W�̐���T�̐����܂����B
�D �`�N�͎c�����R�̐���R���ׂĂ�������̂ŁC�Q�[���ɏ����܂����B
(1) �͂��߂�15�̐�����܂��B��������A�N�͂R�̐����܂����B����B�N�͉��̐����CA�N�̐̎����ɂ�炸�CB�N�͕K�������Ƃ��ł��܂����B
(2) �͂��߂ɂ����40�C41�C42�C43�̂����CA�N�̐̎����ɂ�炸�CB�N���K�������Ƃ��ł���͂��߂̐̌������ׂđI�тȂ����B
(3) �͂��߂ɂ����10�ȏ�100�ȉ��̏ꍇ�CB�N�̐̎����ɂ�炸�CA�N���K�������Ƃ��ł���͂��߂̐̌��͉��ʂ肠��܂����B
�Q�[���̕K���@�Ɋւ�����ł��B�悭��������̂́u�Ō�̐�������l�������v�Ƃ������[���ł����C�{��͂��̋t�ł��ˁB
(1) ����B�N�̎�ԂŁC��15�|3��12(��)�c���Ă��܂��B
B�N���K�����Ƃ������Ƃ́CA�N����������Ƃ��Ă�
�Ō��1����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
1�{6��2�{5��3�{4��7 …… ��
�ɒ��ڂ���ƁCB�N��7�̐��c����
�i5���̐�����ājA�N�Ɏ�Ԃ��悢�Ƃ킩��܂��B
���ہC����A�N�����ׂĂ̐���邱�Ƃ͂ł����C���̎���
B�N�̎�Ԃł��ׂĂ̐���邱�Ƃ��ł��邽�߁C
B�N�͕K�������Ƃ��ł��܂��B
(2) ���ɒ��ڂ��āC�u���O�ɑ��肪������̌��Ƃ�
�a��7�ɂȂ�悤�ɐ���葱����v�Ƃ����헪(��)���l���܂��B
�͂��߂ɂ���̌���7�̔{���̂Ƃ��C
B�N�͕K�������Ƃ��ł��܂��B�Ȃ��Ȃ�C
�����J��Ԃ����ƂŁC�K���Ō�̐���邱�Ƃ��ł��邩��ł��B
����C�͂��߂ɂ���̌���7�̔{���łȂ��Ƃ��C
A�N�͕K�������Ƃ��ł��܂��B�Ȃ��Ȃ�CA�N��1��ڂ�
�u�̌���7�Ŋ������]��v�̌��̐������
�̌���7�̔{���Ƃ��C���̂��Ƃ́����J��Ԃ����ƂŁC
�K���Ō�̐���邱�Ƃ��ł��邩��ł��B
40�C41�C42�C43�̒�����7�̔{����I��ŁC������42���ł��B
(3) A�N���K�������Ƃ��ł���̂́C�͂��߂̐̌���
7�̔{���łȂ��Ƃ��ł��B
10�ȏ�100�ȉ��̐�����91����܂��B���̂���
7�̔{����7×2����7×14�܂ł�13�Ȃ̂ŁC
������
91�|13��78(�ʂ�)
���w�ւ̎Z��
�����o�Ŋ��s
�������̃C���[�W����āA�v�l�͂�b����I
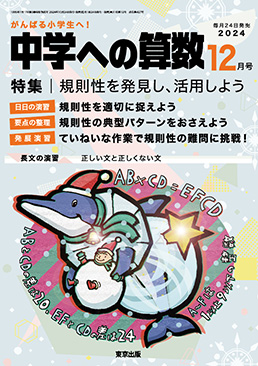
 �ڂ����͂����炩��I
�ڂ����͂����炩��I
���ҏW���j��
�ŋ߂̒��w�����ł́A�^�ɂ������Ȃ��V�X����肪�����Ă��܂��B �����́A���߂�����A����������A����������A�ꍇ������A �K������������A�O���t����������A�}�`��������A ���̂����낢��Ƃ肠��������A�Ƃ����悤�ɁA �P�Ȃ锽�����K�ł͉������Ƃ̂ł��Ȃ��A ���w�I�Ȕ��z�͂�v�l�͂�v���������ł��B ����ɉ�����͂���Ă邱�Ƃ��{���̍ő�̖ڕW�ł��B�����ɁA�𗣂ꂽ�Ƃ���ł��A�Z���̂������낳�A �y������`���Ă����܂��B
�@�ł������ɂ��Ă͂��ꂾ���Ŗ��������A�ł��Ȃ������F�B���u�Ȃ�قǁv�Ɣ[������������N���ł��邩�ǂ��������⎩�����Ă��������B
�@�ł��Ȃ���肪�����Ă��Q���͖��p�ł��B���w�����̎Z���̏o��̔w�i�ɂ́A�����̐�l�����̉p�m�����W���Ă���̂ł��B�u�Ȃ�قǁA����Ȃ�ł��Ȃ����Ƃ�����ȁv�ƃ����b�N�X���āA��l�Ɍh�ӂ�\����“������ӏ�”����C���ŁA���̕M�����������ł���������邩���y���݂Ȃ��猟�����邱�Ƃ��N�̍��Y�ƂȂ�ł��傤�B
�@�C���“�D��S�ƔS��”���������F����ɉ����鐔�w��W�J���܂��B�N�̓��w��҂��Ă��܂��B