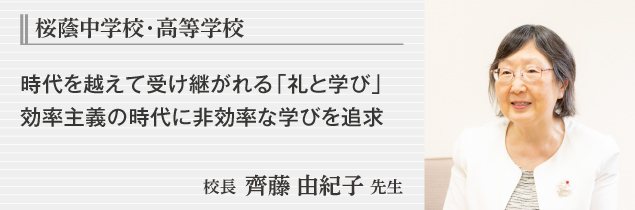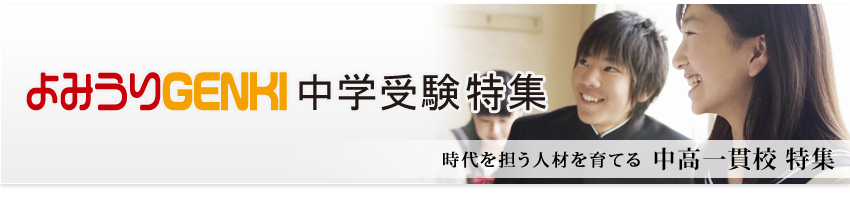
─私立 中高一貫校がいま、考えていること─
実技科目も真剣に取り組む

関東大震災から間もない1924年、東京女子高等師範学校(現お茶の水女子大学)の同窓会「桜蔭会」によって、本校は設立されました。女性が高等教育機関に進むことがまだまだ難しかった時代に、「女性にも男性と同等の教育を受けられる環境を」という強い思いによって建てられた学校です。
建学の精神は「礼と学び」です。この「礼」が表わすのは、宗教に代わる精神的な基盤として、本校が重んじている「礼法」の心です。初代校長の後閑キクノは、礼法を体系的な学問として完成させた人物でした。そのため本校では、創立以来、礼法を学園の独自性を体現する授業として位置づけ、今でも中1の生徒たちは毎週、立礼や座礼、ものの受け渡し方などの基本的な立ち居振る舞いを学んでいます。
次に「学び」の部分で大切にしているのは、どの教科も等しくまじめに学ぶ姿勢です。芸術や保健体育、技術家庭などの実技科目も、大学受験に直結しないからといって疎かにせず、受験科目と同じウエイトで扱うことを徹底しています。
たとえば、中1では週1時間、専門の先生から書道の指導を受けるほか、高1の芸術選択科目では工芸の授業で七宝焼きにチャレンジしたり、音楽の授業で歌曲やオペラ作品を原語で歌ったりします。また、本校は、創立2年目から希望者を臨海学校に連れて行ったという記録が残っているほど、水泳の授業にこだわりを持つ学校です。現在は、2023年に新装されたプールで、専門講師と教員によるチームティーチングで水泳の指導を行っています。
近年、「タイムパフォーマンス」「コストパフォーマンス」ということばをよく耳にするようになりましたが、本校の学びは、そうした効率至上主義とは対極にあるものです。そして、その非効率的な取り組みにこそ、教育活動の意義があると考えています。
あらためて考える平和の大切さ

初代校長の後閑キクノは、自ら教壇に立ち、生徒に礼法と修身を教えていたそうです。それにならい、私も中1の道徳の「桜蔭学園の歴史」という授業を担当しています。
授業のなかで、私は学校に残るさまざまな古い資料を生徒に共有することにしました。特に印象的だったのは、戦時中の生徒たちの様子です。「表向きには英語を勉強することができなくなった」「疎開から戻って来ようと思ったが、桜蔭も空襲の被害を受けたため復学が叶わず、卒業することができなかった」という生々しい記述は、少なからず生徒たちにショックを与えたようです。授業後のアンケートでは「自分たちが英語を自由に勉強できるのは幸せなことだと思った」「先輩たちの気持ちを背負って、がんばって勉強しなければいけないと思った」「戦争の代償をリアルに感じることができた」などと素直な感想をたくさん寄せてくれました。このような悲惨な戦争が起こったことや、未来ある若者が犠牲を強いられたことは歴史の知識として頭に入っていても、実際の先輩たちがどういう思いでその時代を生きていたのか、どのようなことを願っていたのかを知ることは、生徒にとって、このうえない学びになったのではないでしょうか。
平和は、待っていれば誰かが与えてくれるというものではありません。一人ひとりがしっかりと勉強をして、正しい判断力を持って行動することで維持されるものです。「平和を守るためにも、勉強する必要がある」ということは、これからも生徒たちに伝え続けていきたいと思っています。
約60年続く「自由研究」

本校の教育の特色の一つに、中3で取り組む「自由研究」があります。最近は、さまざまな学校で探究活動が盛んに行われていますが、本校が約60年前から続けている「自由研究」は、まさにその先駆けといえるものでしょう。もともとは、「高校受験がない分、何か学びの動機づけになるものを」という発想から始まった試みでしたが、回を追うごとに、「結論が出ない問題についてどう向き合うか」「身の回りから始めた課題解決を、どこまで発展的な活動に進展させることができるか」が生徒たちのメインテーマとなっています。
この「自由研究」では、まず中2の3学期より準備を始め、中3の初めに、テーマや動機を書いた研究計画を提出。そして、テーマに即した文献調査やデータ収集、実験、観察を進め、課題を掘り下げていきます。そして、そこから導かれた結論を「自由研究発表会」で披露するのが最終目標です。
自由研究での取り組みが、国際コンテストで高く評価され、希望進路の実現につながったケースもあります。たとえば、昨年の高3の生徒は、自由研究から発展させた「段ボール箱を再利用した災害時対応 机・折り畳み椅子の設計と製作手法及び手を挟みにくい折り畳み椅子の開発」で、JSEC科学技術政策担当大臣賞を受賞。昨年5月にアメリカ・ロサンゼルスで開かれた世界最大の科学コンテスト「リジェネロン国際学生科学技術フェア(Regeneron ISEF)2024」に日本代表として出場し、見事に優秀賞1等を受賞しました。これは、折り紙から着想を得た、260キロまで耐えられる段ボール製の折りたたみ椅子で、災害時における生活支援や、発展途上国の教育現場への導入が期待されています。このコンテストの実績を武器に、彼女は今秋から海外大学へ進学を決めました。身近なところから社会貢献のアイデアを見つけ、さらにそれを希望進路の実現につなげてくれたことを嬉しく思っています。
中学受験をめざしている小学生の皆さんにお願いしたいのは、勉強を苦役にしないこと。そして、「効率よく得点するために、ここだけ覚えておこう」というような打算的な勉強をしないことです。今は、学ぶ楽しさを身をもって知るための大事な時期です。意欲的かつ積極的に学ぶ姿勢が身につけば、どの学校に行っても素晴らしい学校生活が送れると思います。ぜひ前向きな気持ちでがんばってください。

- 市川中学校・高等学校
- 栄東中学・高等学校
- 佐久長聖中学・高等学校
- 狭山ヶ丘高等学校・付属中学校
- サレジアン国際学園世田谷中学高等学校
- 渋谷教育学園渋谷中学高等学校
- 渋谷教育学園幕張中学校・高等学校
- 西武学園文理中学・高等学校
- 桐蔭学園中等教育学校
- 東邦大学付属東邦中学校・高等学校
- 東洋大学京北中学高等学校
- 東洋大学附属牛久中学校・高等学校
- 広尾学園中学校・高等学校
- 広尾学園小石川中学校・高等学校
- 明治大学付属明治高等学校・明治中学校
- 明星Institution中等教育部
- 立正大学付属立正中学校・高等学校
- 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部・高等部