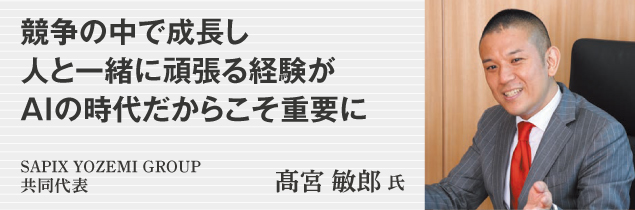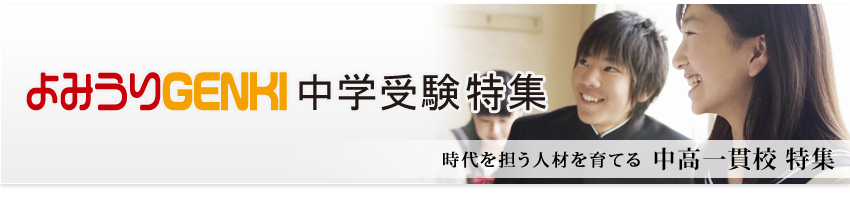
失敗した経験も一つの学びに
あるお笑いコンビが、このようなネタを披露していました。「『わたなべ』という名字は最強だ。五十音順で並んだときに教室の一番後ろの席になるから」。一方、インドでは名前(ファーストネーム)のアルファベット順で並ぶことが多く、「A」で始める名前を付ける親がかなりいるのだそうです。インドでは年間およそ2000万人の子どもが生まれており、その激しい競争の中で、少しでも子どもが有利になるよう、教室の前方に座らせて先生に覚えてもらいたいという親心があるのです。
しかし、インドの大卒者の失業率は29・1%という高さです。大学進学率の上昇に対して、ホワイトカラーの仕事が十分に増えていないことが原因と考えられます。中国も同様の状況にあります。日本の共通テストに相当する試験の受験生は1335万人で、この数は共通テストの約27倍ですが、大卒者の失業率は高くなっています。グローバル化が当たり前の時代ですから、日本人は上昇志向の強いインドや中国の人たちと同じ舞台で戦わないといけないのです。
日本では最近、ある自治体で小学校1年生の通知表を廃止するというニュースがありました。「劣等感を抱かせないように」という理由だそうですが、私はその時点でどういう力を持っているかを把握し、それをもとにどのように伸ばしていくかを考えるのが大切だと思います。競争の中で「頑張ろう」という気持ちが生まれ、うまくいかなかったとしてもその経験から何かを学ぶこともあります。競争の機会が奪われてしまうことには危機感を覚えます。
基本を身に付けるプロセスは必要
AIの活用が一般的になる中で、「今の学びを変えるべきではないか」という議論も出ています。例えば、東京大学の入試問題をAIが解けるからといって、そのための勉強をしなくてもよいのでしょうか。私は入試問題を解くことや、そのための勉強で培われる力があり、それが社会に出てから必要とされる力のベースになると考えています。
確かに、AIの登場により、下調べやリサーチの仕事が効率的にできるようになりました。これらは主に若手が担っていたものですが、仕事の基本を実際にやってみることで身に付くこともたくさんあります。基本を身に付けないまま次のステップに進むと、うまくいかない場面も出てくるでしょう。
AIができるからといって、それを人間が学ぶプロセスとして省略していいわけではありません。早い段階で、社会人として考える作業をしておくことが大切です。中高時代においても、部活動や課外活動などで、仲間と共に何かに取り組む経験は、AIの時代だからこそ、より重要になってくると感じています。
自分をどう表現するか考える
AIの時代は、「人の心をどう動かせるか」が重要になるとも考えられます。そのためには、美術や音楽など「アート」が大きな役割を果たすのではないでしょうか。アメリカやイギリスの学校では、リーダーシップを養ううえで、人の心を動かすためにビジュアルアーツやファインアーツを大事にしています。
海外で日本以上に重視されているのが演劇です。人の前に立ち、人の視線を感じながら、腹から声を出すことは、リーダーとして人前で話すときにも役立つ経験になります。情報技術が進むほど、人に会って何かを伝えられることが重要になるはずです。人を動かす力を持つためには、自分をどう表現するかということが大きく影響してくると思います。
1997年慶應義塾大学経済学部卒業後、三菱信託銀行(現・三菱UFJ信託銀行)入社。2000年、高宮学園代々木ゼミナールに入職。同年9月から米国ペンシルベニア大学に留学して大学経営学を学び、博士(教育学)を取得。2004年12月に帰国後、同学園の財務統括責任者、2009年から現職。SAPIX小学部、SAPIX中学部、Y-SAPIXなどを運営する日本入試センター代表取締役副社長などを兼務。

- 市川中学校・高等学校
- 栄東中学・高等学校
- 佐久長聖中学・高等学校
- 狭山ヶ丘高等学校・付属中学校
- サレジアン国際学園世田谷中学高等学校
- 渋谷教育学園渋谷中学高等学校
- 渋谷教育学園幕張中学校・高等学校
- 西武学園文理中学・高等学校
- 桐蔭学園中等教育学校
- 東邦大学付属東邦中学校・高等学校
- 東洋大学京北中学高等学校
- 東洋大学附属牛久中学校・高等学校
- 広尾学園中学校・高等学校
- 広尾学園小石川中学校・高等学校
- 明治大学付属明治高等学校・明治中学校
- 明星Institution中等教育部
- 立正大学付属立正中学校・高等学校
- 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部・高等部